
小学生のとき、学校の授業で「春の七草」を習ったことはありませんか?
5・7・5・7・7のリズムに合わせて覚えたり、写真を見てどんなものなのか覚えたかと思います。
しかし大人になって、春の七草の全てを言える人は少ないかと思います。
そこで今回は春の七草がどんなものなのかを詳しく掘り下げていきますので、最後までお付き合いください。
春の七草とは?

春の七草は、七草粥として食すための7つの食物になります。
七草粥は、毎年1月7日(人日の節句)に春の七草を入れて食べるお粥のことです。
七草は早春にいち早く芽吹くことから、邪気を払うといわれていました。
そのため、七草粥を食べることで、1年の無病息災を祈るようになったのです。
この習慣は江戸時代から始まったようです。
春の七草の時期ですが、春と言うと3~4月ころを想像しますが、春の七草(七草粥)が食べられるようになった時代は旧暦のため、現在の2月上旬~3月と推定されます。
また、七草粥は中国の風習が由来とされています。
中国が唐と呼ばれていた時代、1月7日の「人日の節句」に七種菜羹(しちしゅさいこう、しちしゅのさいこう)という7種類の野菜が入った汁物を食べて無病息災を願う風習があったそうです。
この「人日の節句」と日本の風習としてあった「若菜摘み」が合わさって七草粥になったと考えられています。
ちなみに、七草は時代や地域によって異なることもありますが一般的に、
セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ
を指します。
おせち料理が続き、正月疲れが出はじめた胃腸をいたわり、回復させるにはちょうどよい食べ物です。
また、青菜の不足しがちな冬場の栄養補給も行なうという目的もあったようです。
これらの植物のうち、ゴギョウはハハコグサ、ハコベラはハコベ、ホトケノザはコオニタビラコ、スズナはカブ、スズシロはダイコンのことです。
カブとダイコンは畑で栽培されている野菜ですが、残りの5種類は身近な場所に生えている野草になります。
セリ
セリは、別名シロネグサとも呼ばれるセリ科の植物です。
競り合うように生えていることから、この名がついたそうです。
独特の香りが食欲を刺激する効果があり、尚且つ栄養価が高いのも特徴です。
血液をきれいに保ち、高血圧や動脈硬化の抑制にも作用します。
さらには胃腸の調子を整えるという整腸効果も持っており、ビタミンA、ビタミンC、カルシウム、リン、カリウムが含まれる食材なのです。
ナズナ
ナズナは、麦栽培の伝来とともに日本に伝わったとされる史前帰化植物になります。
ナズナはぺんぺん草とも呼ばれています。
こちらの名前の方が聞き覚えがある方が多いかもしれません。
花の下についている果物の形が、三味線のばち(弦楽器の弦をはじくための道具)に似ていることが、この呼び名に由来します。
古くから民間療法で用いられてきた植物でもあり、高血圧・解熱・便秘・利尿・解熱・止血作用に効果があるといわれています。
特にビタミンKが豊富に含まれ、骨粗しょう症の改善効果が期待されています。
煎じた汁で洗眼すると目の充血や痛みを和らげる効果があるともされています。
ゴギョウ(ハハコグサ)
ゴギョウは朝鮮半島から伝わったとされている、キク科の植物です。
明治時代ごろまで草餅の食材として利用されていました。
茶にして飲むこともあり、咳止め・痰きり・喉の炎症・利尿・むくみに効果があるとされています。
ハコベラ(ハコベ)
ハコベラは、ナデシコ科の植物です。
中国では古くから薬草として使われていましたそうです。
効能は七草の中でも多く、利尿作用・止血作用・鎮痛作用をはじめ、歯槽膿漏の予防薬として使用されてきた歴史があります。
ビタミンB群やビタミンC、カルシウム、カリウムに加え、カロテノイドやフラボノイド、サポニンが含まれる非常に栄養素の豊富な薬草です。
ホトケノザ(コオニタビラコ)
ホトケノザは、キク科の植物です。
効能として、健胃・整腸作用、高血圧予防などがあるとされています。
食べ方としては塩ゆでした後に流水にさらし、苦みなどを取り除いてから使用します。
また、シソ科でホトケノザという植物もありますが、こちらは全くの別ものです。
キク科のホトケノザは黄色い花を咲かせるのに対し、シソ科のホトケノザはピンクの花を咲かせるので、見た目も異なります。
※シソ科のホトケノザは食べられませんのでご注意ください。
スズナ(カブ)
スズナはアブラナ科の植物です。
カブの方が耳馴染みがある名前かと思います。
カブは便秘・胃潰瘍・胃炎・風邪・骨粗鬆症・がんの予防に良いとされています。
そのため、胃腸の調子が悪いときに食べられてきました。
根の部分と葉っぱの部分でそれぞれ効能を持っており、特に葉にはビタミンA、B1、B2、C、カルシウム、鉄、食物繊維が豊富に含まれています。七草粥を作るときは両方入れることをおすすめします。
スズシロ(ダイコン)
スズシロは、現代では大根としておなじみの食材です。
栄養素としては、ビタミンA、C、食物繊維、ジアスターゼ、アミラーゼ、フラボノイドが含まれ、根と葉両方に栄養が詰まっています。
消化不良や二日酔い、頭痛、発熱、冷え性、胃炎、便秘の解消など他にも様々な効能が期待されています。
根の部分に特にジアスターゼが多く含まれ、食物の消化を促進してくれます。
一方、葉にはビタミンやミネラルが多く含まれているため、両方とも七草粥に入れると良いですが、市販の大根の葉には農薬などが付着している可能性があるため、きちんと洗うなどしてから食すようにしましょう。
七草粥の作り方&体に良い5つの理由

次に、七草粥の基本レシピをご紹介いたします。
七草粥は地域によって作り方も違えば、プラスで入れる食材も違いますので、ご自身にあった七草粥を作って食べてみて下さい。
また、七草粥の時期になると、スーパーなどで七草粥用のセットパックが売られるようになります。
バラバラに購入すると手間がかかったり、使い切れなかったりすることもあるので、こういったセットパックを購入するのもおすすめです。
材料(2.3人分)
・米 1/2合
・水 600ml
・春の七草 市販品1パック
・塩 ふたつまみほど
1度も食べたことが無い、という方はぜひ挑戦してみてください。
胃に優しく、体も温まります。
!ワンポイント!
七草粥は地域によって違いがあります。
具材が春の七草でなかったり、お粥でなかったりなど様々です。
東北地方のように雪深い地域では、かつて七草が手に入りにくかったため、ニンジンやダイコン、ゴボウといった根菜類やコンニャク、厚揚げなどが入っています。
また、山形県の一部地域で1月7日に食べられているのは、キノコや山菜、厚揚げ、豆腐、コンニャクなどが入った納豆汁です。
だし汁と具材を煮て、味噌で味付けをした後にすりつぶした納豆を入れてとろみをつけます。
九州では具材にクジラ肉やブリを入れる地域もあります。
そして体にに良い5つの理由ですが、こちらになります。
①ビタミンとミネラルの豊富な栄養補給
先述しましたよつに、七草にはビタミンA、C、E、Kやカルシウム、鉄、マグネシウムなどが含まれています。
これらの栄養素は体の機能や代謝に必要であり、七草粥はこれらをバランスよく摂取できる食品です。
②消化器官のサポート
七草粥は粘性があり、食物繊維も含まれています。
これにより、胃腸の動きが促進され、食事の消化がスムーズに行われます。
③デトックス効果
七草には有害な物質を排除する働きがあり、特に新年や季節の変わり目に摂取することで、体内の不要な物質を排除し、健康な状態を維持できます。
④ 免疫力向上
七草には抗酸化物質が含まれており、これが細胞を守り、免疫機能を向上させます。
感染症や風邪などから身体を守る役割が期待できます。
⑤ 体温調節と冷え対策
七草粥は体を温める性質があり、特に寒冷な環境での摂取は体温を維持しやすくします。
これにより、冷えからくる不調を軽減することができます
春以外の七草
七草は春だけではなく、それぞれの季節にあります。
秋の七草
オバナ(ススキ)・オミナエシ・キキョウ・クズ・ナデシコ・ハギ・フジバカマ
春と並んで有名なのが秋の七草です。
万葉集に収められている奈良時代の歌人、山上憶良(やまのうえのおくら)が詠んだ和歌が由来とされています。
秋の七草は食べるのではなく、植物を鑑賞して季節を感じるものになります。
秋の七草の場合、旧暦の7~9月がその時期と言われています。
現在では7~9月は夏のイメージが強いですが、旧暦と新暦では1ヵ月ほどズレがあります。
夏の七草
ヨシ・イ(イグサ)・オモダカ、ヒツジグサ、ハス、コウホネ、サギソウ
夏の七草は、実は他にもいろいろな組み合わせがあります。
また夏の七草は、戦時中の食糧難によって選定され、時期としては初夏から晩夏となる5~9月頃となります。
冬の七草
ネギ・ハクサイ・ダイコン・シュンギク・ホウレンソウ・キャベツ・コマツナ
冬の七草は草よりも冬野菜という印象もあります。
夏と同じように、いくつかの組み合わせがあります。
代表的な野菜が多いため、全てを口にしたことがある方がある人の方が多いかと思います。
ちなみに冬の七草は旧暦の時代に作られたものではなく、新暦の現代に始まったものになります。
そのため、12~2月を冬の七草の時期と考えてよいでしょう。
まとめ

春の七草、全てを思い出すことができましたでしょうか。
大人になってから改めて七草の名前をみると、こんな食材だったんだ、と新たな発見もあったかと思います。
これを機に、春の七草、七草粥に興味を持っていただけたらと嬉しく思います。
そして「みんなで農家さん」では、農業が好きな方、農家を志す人、農業従事者の方へ役立つ、最新情報やコラム、体験談などをこれからもお届けいたします。
あなたの気になる情報が、もしかしたらここにあるかもしれません。
こんな情報が欲しい、あんな情報が載っていないかな? と気になった方、まずは一度覗いてみてください。
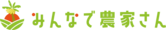



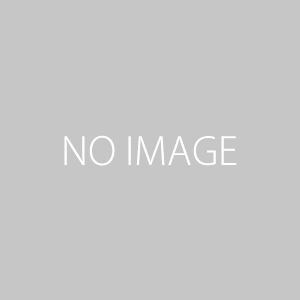


コメント